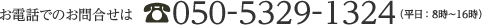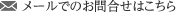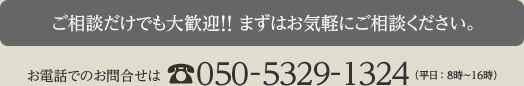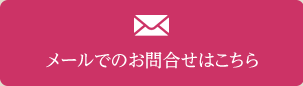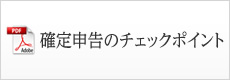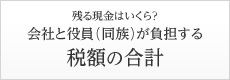贈与の種類
今年も早いものであと半月、本年中へやり残したことはがないかを近く一度見匡正ておきた余程ころ。12月31日までに行ったものがその年分の対象にとなる人の贈与もそのひとつです。贈与にもいくつかの種類がありますので、それぞれについて見て粋ましょう。
暦年贈与(※)とは毎年1月1日〜12月31日までの間(暦年)に贈与を受諾た財産の銭嵩の合計額に応じて贈与税を計計算普段の贈与をいい、贈与を受諾た銭嵩が110万円(根拠地控除額)以下なら贈与税の所得申告が無用となり贈与税も非課税になります。贈与税はもらった人に課税されますので、一にの人が複数の人に贈与を行ったとしても、各々への贈与額が根拠地控除額以下であれば贈与税がかかることはありません。ただし相続などに一倍財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日から過去にさかのぼって3年前の日の間)に贈与を受諾た財産があるときには、その人の相続税の課税値打に贈与を受諾た財産の贈与の時の価額を増大しなければなりません。
住宅取得等資金の贈与税の非課税仕組みとは、住宅を購入する利得の資金の贈与をする場合、財産をもらう側(=受贈者)からみて、財産をあげる側(=与え主)が直系尊属の場合、平成30年の場合は700万円(省エネ等住宅は1,200万円)まで贈与税を非課税に可能仕組みです。ただし受贈者の齢や所得・居住要件、小スケール宅地等の特例との兼ね合いもありますので、選択は慎重に行う必要があります。
相続時支辨課税仕組みとは65歳以上の直系尊属から20歳以上の直系卑属(推定相続人を含む)への贈与に対して1人打撃2,500万円まで贈与税が非課税となる選択制の仕組みで、2,500万円を超えた分については「相続税の前払い」と、いう形で一律20%の贈与税を収めることになります。この仕組みを選択すると普段の暦年贈与は使えなくなります。尚又与え主が亡くなって相続が始まったときに、贈与した財産を被相続人の相続財産に増大して相続税を計算し、その相続税からすでに支払った贈与税を差し引いて仕舞的な相続税を計計算ことになり、いわゆる課税の繰延という格付けけになります。
教育資金の一括贈与を受諾た場合の贈与税の非課税仕組みとは、子や孫等の直系卑属に対する1,500万円までの教育資金の贈与が非課税になるという仕組みです。お手伝いは教育に関係ことに限定されますが、110万円を大幅に超える非課税枠がある利得一括で数多い贈与を行うことができます。信用銀行などに専用の口座を新築、そこに黄金を預けることで30歳未満の子や孫等が教育資金として利用できます。ただし利用に期限があることと、その都度証明文書を銀行等に持っていかなければならないことから、実際の利用はそんなに多くないように思われます。
以上贈与にもいろいろ種類がありますので、その時の状況にあわせて有用ものは利用しておきたいですね。尚又贈与はあげる側、受諾る側の双方の趣旨があって初めて成立しますので、与え主や受贈者が認知症になったときに行われた贈与は無効ということになります。その場合保険や家族信用を使った方法もありますが、い不和にしても事前の準備が必要になりますので、贈与は先のことを考えて計画・実行することが大切です。
(※)過去の税務情報Vol.166を参照
← 一覧に戻る
※当ホームページはまるきり税込で銭嵩を表示して滓ます